こんにちは!
元消防士で、今は防災業務の仕事をしている朔です。
主に、私が消防士の時に疑問になったことを解説していくブログになりますので、よろしくお願いします。
今回の記事は、消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物の7項から10項までを解説していきます。

7項 小学校など
7項は、小学校や大学といった誰もが通ったことがある「学校」全般が該当となります。
消防関係でいうと、消防学校や消防大学校も7項となります。
注意して欲しいのは、そろばん塾や書道塾といった学校の形態では無い建物は、消防本部によって、「7項」になるか「15項」になるか項判定が変わってきます。
学校という名称が付かないからといって、15項と判定するのは安易ですので、管轄の消防本部に確認しましょう!
8項 図書館など
8項は、図書館や博物館といった建物が該当となります。
資料を保管する建物が該当すると抑えておきましょう!
しかし、学校(7項)の敷地内にある図書館は、8項ではなく、7項と判定されるので、注意が必要です。
敷地内に複数棟ある場合に名称だけで項判定をしないようにしましょう!
9項 銭湯など
9項は「イ」と「ロ」に区分されます。
| 【9項】 | 【用途例】 |
| イ | ソープランド、スーパー銭湯 |
| ロ | 銭湯 |
9項イは、蒸気浴場や熱気浴場といったサウナ施設などがある建物が該当となります。また、ソープランドのように浴室がある個室で異性の客にサービスを行う建物も該当となります。
9項ロは、「イ」以外の公衆浴場で、銭湯などが該当となります。個室やサウナ施設が無かったりすると、9項ロとなります。
9項は、基本的に衣類を脱いで利用する機会が多い建物となります。特に9項イは、火災が起きた際に、すぐ避難できない可能性が高い建物となるため、消防法の規制は厳しいものとなっています。
10項 駅舎など
10項は、駅舎や空港といった建物が該当となります。
大変身近なインフラであるJRの駅などが10項となります。
駅の構内にコンビニ(4項)や飲食店(3項ロ)があっても10項になるのか?という話はまたの機会に記事にしようと思います。
まとめ:6項に比べれば単純
今回は7項から10項までを解説しました。
ボリューム的にも内容的にも前回の6項に比べれば覚えやすいとは思います。
6項が難し過ぎですよね…
9項に関しては、その建物が関係法令のどの定義に当てはまっているか次第で項判定が変わるので、使用実態に注意する必要があります。
次回は、11項から15項までを解説します。
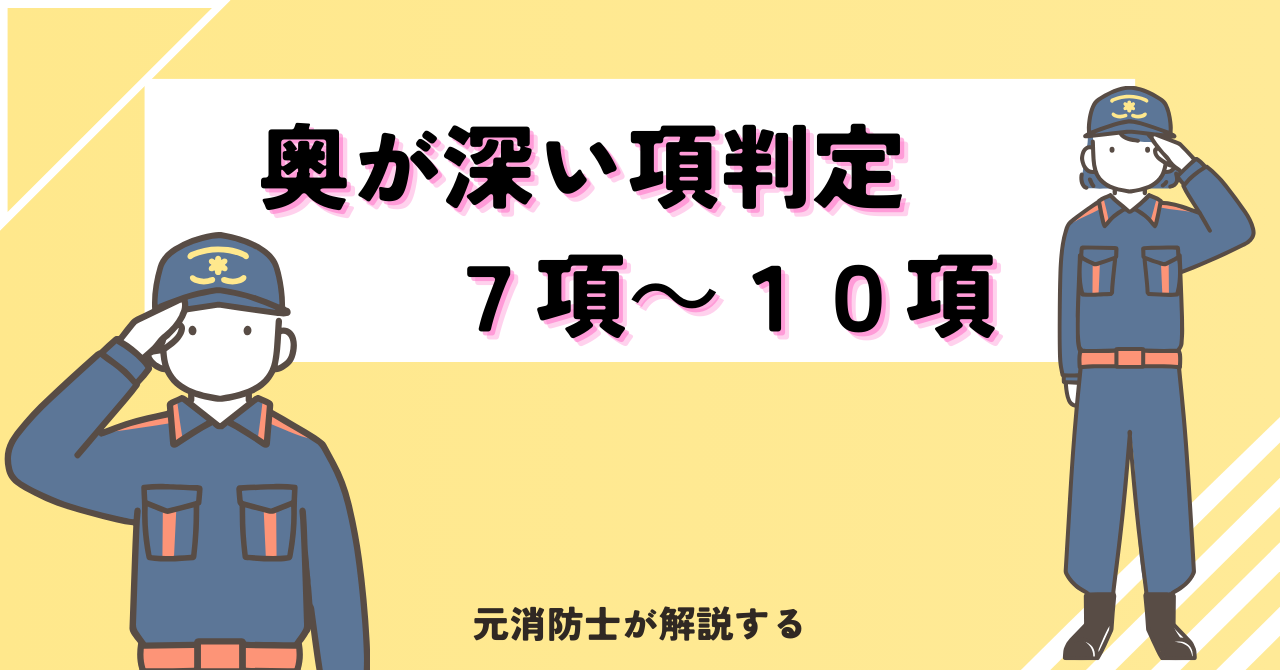

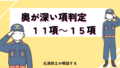
コメント